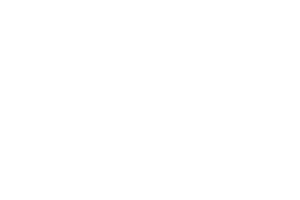畳にこぼれる午後の光が、彼女の袖をやわらかくなぞる。
薄紅の着物は呼吸に合わせて揺れ、結び目の帯が、まだ言葉にならない約束を静かに抱きしめている。
黒髪に差す簪が小さく鳴り、時間は少しだけ遅く流れた。
障子を渡る風が、花の香りをひとすじ運んできた。
振り向いた微笑みは、遠い季節の記憶を起こす合図のようで、胸の奥に小さな灯りを点す。
触れずとも伝わる温度が、今日という一日の余白をやさしく満たしていく。
夕暮れが縁側を染めるころ、彼女はそっと裾を整え、目を伏せた。
その仕草だけで、まだ見ぬ明日の頁が一枚、音もなくめくられていく。