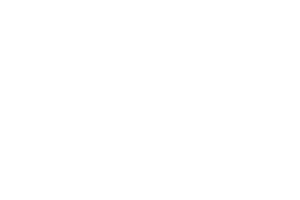薄暗い台所に、風がすり抜けるたび、古い冷蔵庫がブーと唸る。
彼女はまな板の上に光る包丁を置き、刃の呼吸を確かめるように指で柄をなぞる。
切るのは恐れ、刻むのは昨日の影だ。
窓の外で鈴が鳴り、夜はさらに深くなる。
彼女は一歩だけ踏み出し、深呼吸をひとつ。
静寂は背後から寄り添い、氷のような金属に映る自分の輪郭が、やわらかく揺れて消えた。
包丁は静かに横たわり、夜の音を分ける境界のように細く光る。
彼女は電気を落とし、窓に映る街明かりを見つめた。
ブーという低い響きが遠のくと、鼓動だけが、確かな現在をたしかめていた。