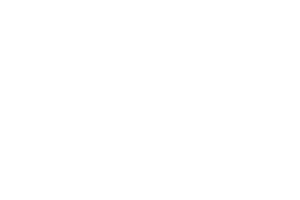灯りはやわらぎ、彼女の曲線だけが部屋に残る。
豊かな胸元は呼吸に合わせて静かに持ち上がり、落ちる。
その柔らかなリズムが、夜の秒針をゆっくり進めていく。
レースの縁が肌に淡い影を描き、視線はそこにそっと留まる。
言葉より先に、鼓動が小さく返事をする。
触れないままの距離が、いちばん雄弁だと知る。
彼女は髪を耳にかけ、肩をすべらせるように息を吐く。
香りは薄く、しかし確かで、胸の奥でほどけた。
窓辺の風が揺らすのはカーテンか、それとも期待か。
見せるためではなく、見つめられることへの静かな誇りが、微笑みに宿っていた。