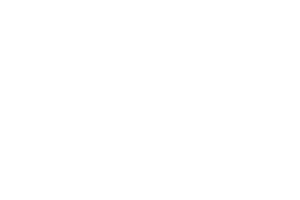大きなリボンを揺らしながら、彼女は手持ち花火を掲げる。
ぱちぱちと弾ける音が、遠い花火大会の余韻を呼び戻し、煙の香りが夜のページに薄い色を差していく。
レンズの向こうで、静かな笑みがほどけた。
火花は瞬きのように短く、しかし確かに軌跡を残す。
彼女はその光で自分の輪郭をなぞるように、夏の片隅に小さな約束を書き込む。
消えても残るものを、今夜だけは信じてみたくなる。
風にほどけたリボンが、また結び直されるたび、ページの隅に栞が増えていく。
撮る人も撮られる人も、同じ夜をそっと分け合い、火花の終わり際に次の季節を思った。