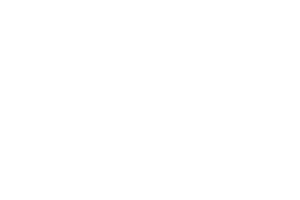カーテンが呼吸するたび、薄い影が壁を渡っていく。
マグの縁に残る熱が、まだ言えない言葉の温度を測るみたいで、ふたりの指先はテーブルの木目をなぞるだけ。
名前を呼ぶ声は小さく、それでも確かに、午後の光に溶けた。
沈黙は距離を作らず、輪郭をやわらかくする。
視線が触れて、すぐ離れて、また戻る。
その往復のあいだに、これからの約束が静かに芽ばえる。
窓越しの空は淡く、時間だけが丁寧に進んでいった。
やがて外の鳥が一度鳴いて、笑いがほどける。
「もう少しここにいよう」——誰が言ったのかは曖昧なまま、湯気は細く背伸びをして、同じ高さで止まった。
部屋は狭いけれど、ふたりには充分な広さだった。