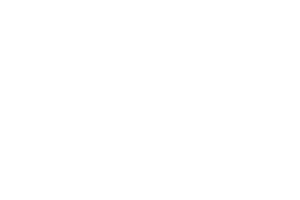灯りの落ちた部屋、彼女は刃を握り、自分の鼓動を数えていた。
窓の外の夜風が薄くカーテンを揺らし、月の白さが床に細い道を描く。
彼女は逃げるためではなく、迷いを断つために、そのひと筋の冷たさを頼った。
震えは恐れではない。
過ぎ去った日々の影に、やっと言葉を与える準備の合図。
刃は脅しではなく、境界を知るための鏡。
深く息を吸い、吐くたび、彼女の輪郭は静かに整っていく。
やがて夜は浅くなる。
最初の鳥の声が届く頃、彼女は手を下ろし、窓を開けた。
冷たい空気に頬を晒し、新しい朝の光に目を細める。
切っ先よりも鋭いのは、背筋を伸ばす意志だけだった。